
BIMデータは、建築業界におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する重要な技術です。単なる3Dモデルにとどまらず、建物に関する多様な情報を内包しており、企画・設計・施工・維持管理といった建築プロジェクトのあらゆる段階で活用されています。本記事では、BIMデータの基礎から3D CADとの違い、活用方法、導入メリット、必要なツール、そして今後の展望までを詳しく解説します。
BIMデータとは
BIM(Building Information Modeling)データとは、建築物の3Dモデルに、建材の材質・性能・コスト・設備機器の情報など、さまざまな属性を付加したデジタルデータです。単なる形状データではなく、建物情報の一元管理を担う「データベース」として機能します。企画・設計から施工・維持管理まで、建物のライフサイクル全体にわたって活用されることで、情報共有の効率化、業務の合理化、コスト削減などが期待されます。国土交通省もBIMの導入を積極的に支援しており、今後の建築業界においてBIMデータは欠かせない存在になるでしょう。
3D CADとの違い
BIMと3D CADはどちらも立体的な設計を行うツールですが、モデルの作成方法や活用範囲、管理できる情報量に大きな違いがあります。以下に主な違いを解説します。
モデル作成方法の違い
3D CADは、まず2次元の平面図や断面図を作成し、それを基に3Dモデルを構築する手法が一般的です。一方でBIMは、最初から3Dモデルを構築し、そのモデルから自動的に平面図や立面図を切り出すという、逆のアプローチをとります。BIMでは壁・柱・窓などの建築部材を「オブジェクト」として配置し、それぞれに属性情報を付加します。この違いにより、BIMは図面作成だけでなく情報管理や業務効率化にも大きく貢献します。
情報量と活用の違い
3D CADが主に建物の形状や寸法といった幾何学的な情報に特化しているのに対し、BIMはそれらに加えて、壁の材質、窓ガラスの性能、設備機器の型番、家具の種類や製造元、さらには製品のコストやメンテナンス履歴など、建築物に関する非常に広範かつ詳細な非幾何学的な情報を管理できます。BIMモデルは単なる3Dモデルではなく、建物に関するあらゆる情報を統合したデータベースとして機能するため、設計段階での詳細な検討はもちろん、建材の発注や工事のシミュレーション、さらには建物の完成後の維持管理や運用まで、プロジェクトの全ての段階でこの情報 richなモデルを活用できます。
例えば、BIMでは建材一つ一つに価格情報を持たせることができるため、設計変更を行った際にリアルタイムでコストへの影響を確認できます。また、家具についてもメーカーや型番、価格といった情報をモデルに付加することで、インテリアの検討から発注、資産管理までを効率的に行うことが可能です。このように、BIMは単なる設計ツールを超え、建築物のライフサイクル全体をサポートする「建築情報モデル」として機能し、プロジェクト全体の効率化と品質向上に大きく貢献します。
設計変更への対応
設計変更が発生した場合の対応において、BIMと3D CADでは大きな違いがあります。3D CADで作成されたモデルや2次元図面の場合、どこか一部を変更すると、それに関連する他の図面やビューを手作業で修正する必要が生じ、修正漏れや整合性の不一致が発生するリスクがありました。これは、それぞれの図面が独立して作成されているためです。しかし、BIMでは3次元モデルとそこから生成される各種図面や集計表などが一元管理されています。そのため、3次元モデル上の情報を修正すると、関連する全ての図面やデータにその変更が自動的に反映されます。これにより、修正作業の手間が大幅に削減され、図面間の整合性が保たれやすくなり、設計変更による手戻りやミスを最小限に抑えることが可能となります。
BIMデータの活用方法
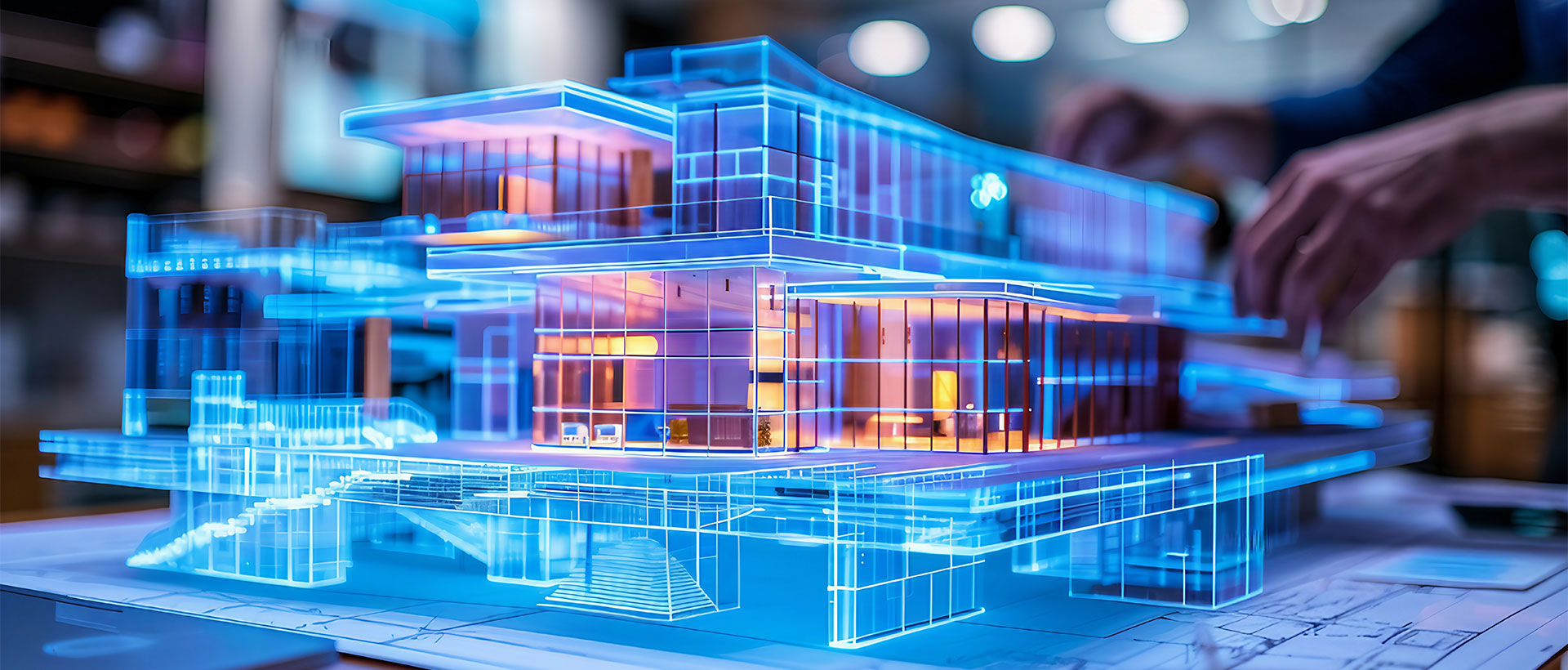
BIMデータの活用は、建築プロジェクトの様々な段階で多岐にわたります。単なる設計ツールとしてだけでなく、プロジェクト全体の効率化や関係者間のコミュニケーション促進に貢献します。以下に主な利用シーンを紹介します。
設計・施工段階での活用
BIMデータは、設計段階では建物の詳細な3次元モデルを作成し、デザインの検討や各種シミュレーションに活用されます。関係者間で完成イメージを容易に共有できるため、合意形成を迅速に進めることができます。施工段階では、BIMデータをもとに詳細な施工計画を立てたり、部材の干渉チェックを行ったりすることで、手戻りやミスの削減につなげられます。また、BIMモデルから直接、部材の数量や仕様を把握できるため、積算や発注業務の効率化も実現します。
シミュレーションへの活用
BIMデータに含まれる豊富な情報を用いて、様々なシミュレーションを実施することが可能です。例えば、日照シミュレーションにより、建物の配置や窓の大きさ、庇の出幅などが室内の明るさや温度にどのように影響するかを分析できます。また、エネルギー消費量のシミュレーションを行えば、省エネルギー性能の高い設計を検討する上での有効な情報が得られます。さらに、建築業界ではBIMデータに時間軸の情報を加えた「4DBIM」による工程管理シミュレーションや、コスト情報を加えた「5DBIM」によるコスト管理、そして建物の運用・維持管理情報を加えた「6DBIM」によるライフサイクルマネジメントなど、より高度な活用が進められています。これらのシミュレーションにより、設計段階で潜在的な問題を事前に発見し、最適な意思決定を行うことが可能になります。
BIMデータを活用してデジタルツインを構築
https://www.cadcenter.co.jp/works/archives/10373/
竹芝エリアの防災まちづくりに関する実証実験では、発災時の情報共有や施設管理の課題を解決するため、3D都市モデルとBIMデータを活用したデジタルツイン環境が構築されました。キャドセンターは、東京ポートシティ竹芝のBIMデータをベースに、建物外観を高精度に再現するための加工やテクスチャ追加を行い、国土交通省が定める「LOD4相当」の高精細な3D都市モデルを作成。これにより、建築物ごとの視認性や情報認識の精度が向上し、防災・避難に関する意思決定を支援するリアルな仮想空間を実現しました。
情報共有と合意形成
BIMデータは、建築プロジェクトに関わる設計者、施工者、施主、さらには将来の維持管理者といった多様な関係者間での情報共有を円滑にします。3次元モデルによって建物の完成形を視覚的に分かりやすく提示できるため、専門知識を持たない人でもプロジェクトの内容を容易に理解できます。これにより、関係者間の認識のずれを防ぎ、円滑なコミュニケーションと迅速な合意形成を促進します。特に複雑なプロジェクトにおいては、BIMデータが「共通言語」となり、関係者全員が同じ情報を参照しながら議論を進めることが可能となります。
BIMデータを教育訓練に活用
https://www.cadcenter.co.jp/works/archives/2202/
BIMデータを活用し、ALC(軽量気泡コンクリート)の施工手順を精緻な3DCGで再現した教育映像を制作しました。BIMに基づく高い再現性により、効率的かつ実践的な教材が実現。施工プロセスの可視化によって、教育や技術継承の現場ニーズに応える内容となっています。
維持管理・運用段階での活用
建物の完成後も、BIMデータはその価値を発揮します。BIMデータには、建材の仕様、設備機器の型番、メンテナンス履歴、保証期間など、建物の維持管理や運用に必要な情報が含まれています。これらの情報をBIMモデルと紐づけて管理することで、修繕計画の立案、点検箇所の特定、部品交換時期の把握などを効率的に行うことができます。例えば、特定の設備に不具合が生じた場合、BIMデータを確認することで、その設備の詳細情報や過去の修繕履歴を迅速に把握し、適切な対応をとることが可能になります。このように、BIMデータは建物のライフサイクル全体にわたる情報管理を支援し、長期的な維持管理コストの削減や資産価値の維持に貢献します。
BIMデータ活用のメリット
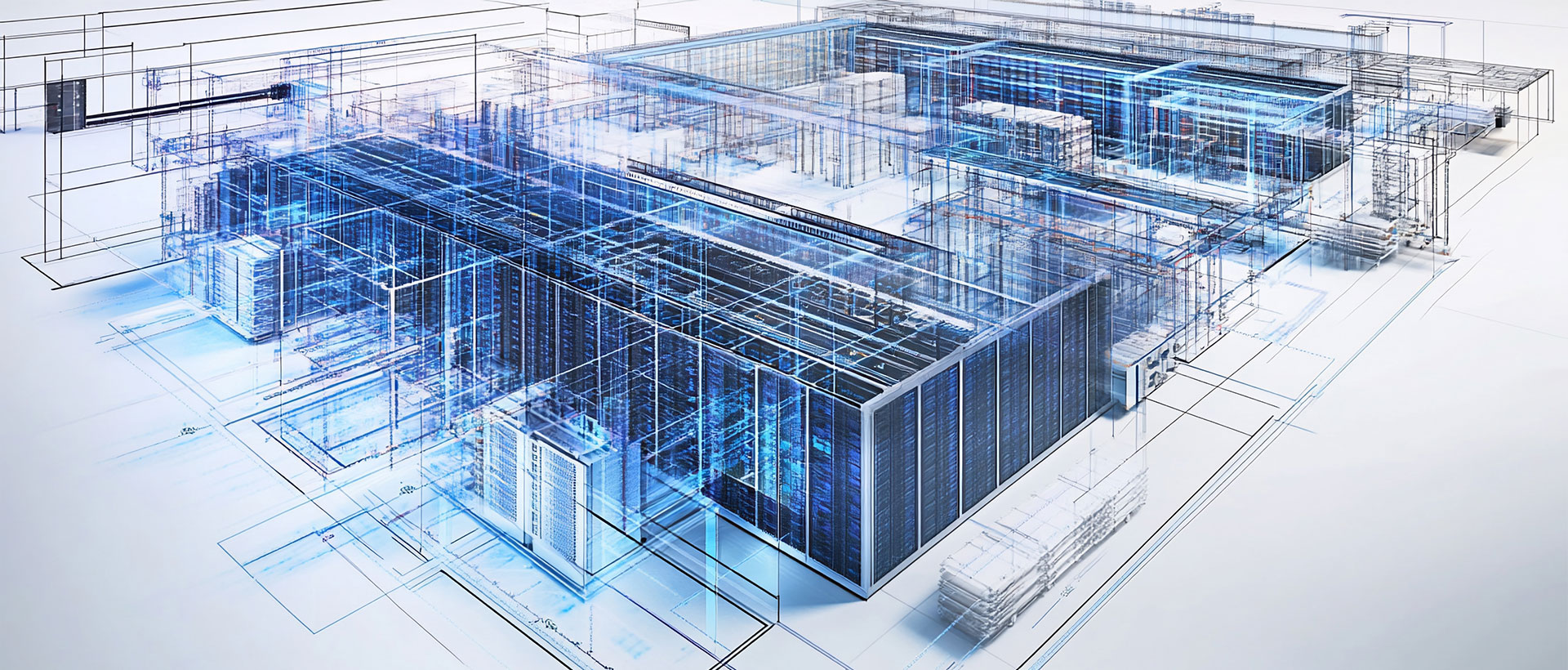
BIMデータの活用は、建築・建設業界に様々なメリットをもたらします。これらのメリットは、プロジェクトの効率化や品質向上、そして収益性の向上に大きく貢献します。
コスト削減の可能性
BIMデータを活用すると、プロジェクト全体でコスト削減に繋がる可能性があります。設計の早い段階で詳細な3次元モデルを作成することで、設計ミスや手戻りを減らせます。これにより、修正にかかる時間や費用を抑えることができるでしょう。 また、BIMデータから正確な数量を算出できるため、資材の無駄な発注を防ぎ、コスト削減に貢献します。 さらに、維持管理の段階でも、効率的な情報管理によってメンテナンスコストの最適化が図れます。 実際の事例として、BIM導入により発注金額が平均1.41%削減されたという報告もあります。
業務効率と生産性の向上
BIMデータの導入は、業務効率と生産性の向上に大きく寄与します。3次元モデルから各種図面や集計表が自動で生成されるため、従来手作業で行っていた作業時間を削減できます。設計変更があった場合も、関連情報が自動更新されるため、修正作業の手間が大幅に軽減されます。また、関係者間での情報共有が円滑になることで、コミュニケーションロスによる手戻りや誤解を防ぎ、プロジェクト全体の進行をスムーズにします。これらの効率化により、限られた時間内でより多くの作業をこなせるようになり、生産性の向上につながります。
BIMデータの入手と利用
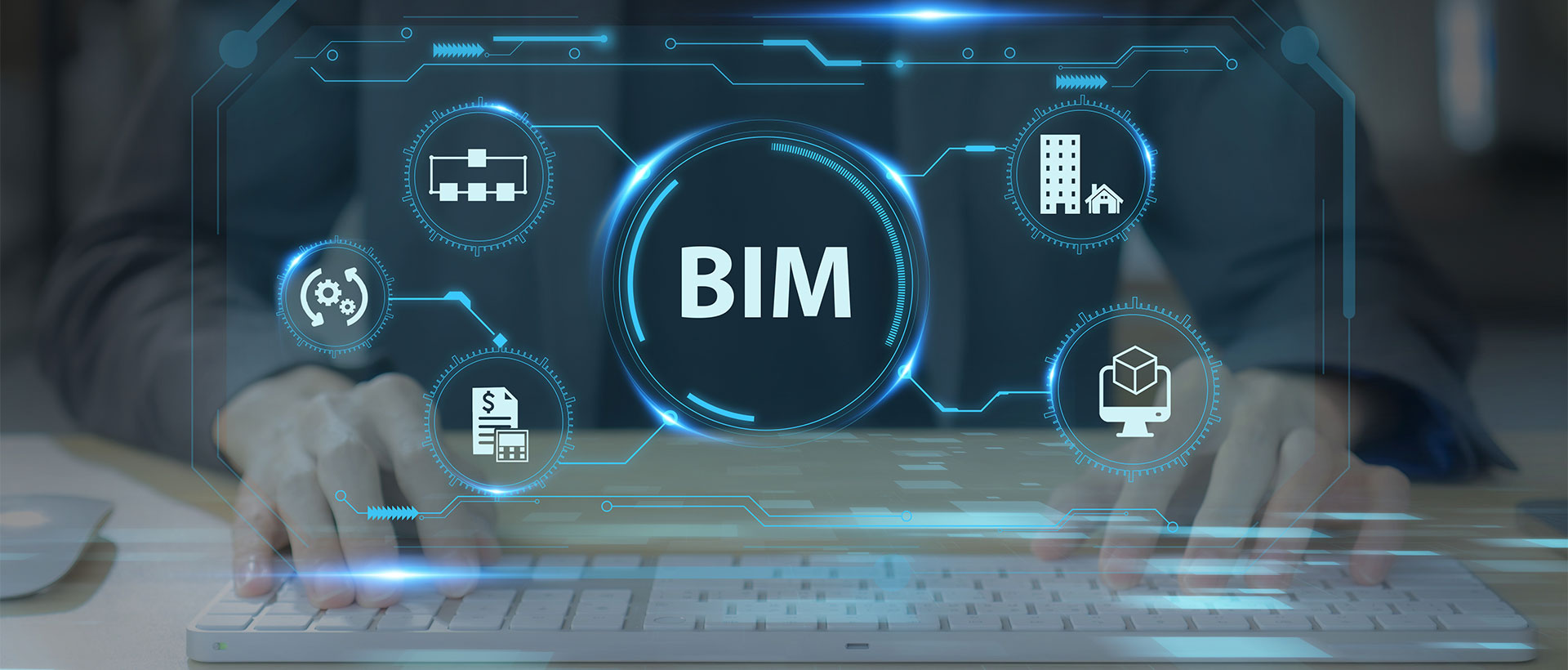
BIMデータを実際に利用するためには、データの入手方法や、データを閲覧・編集するためのソフトウェアが必要です。ここでは、それらの方法について解説します。
BIMデータの入手方法
BIMデータの入手方法はいくつかあります。まず、建材メーカーや設備メーカーが自社製品のBIMデータをWebサイトで提供している場合があります。これらのサイトから必要なデータをダウンロードして利用できます。また、BIMオブジェクトの総合ライブラリサイトも存在し、様々なメーカーのBIMデータを一括して検索、ダウンロードすることが可能です。中には無料またはフリーで利用できるデータも多く提供されています。ただし、利用規約を確認し、商用利用が可能かなどを確認することが重要です。さらに、自社でBIMソフトウェアを用いてオリジナルのBIMデータを作成することも可能です。
BIMデータ利用に必要なソフトウェア
BIMデータを活用するには、専用のソフトウェアが不可欠です。これらのソフトウェアを用いることで、3次元モデルの閲覧や編集、属性情報の確認が可能になります。主要なBIMソフトウェアには、Autodesk RevitやGraphisoft ARCHICAD、福井コンピュータアーキテクト GLOOBEなどがあり、それぞれ得意とする分野や機能が異なります。プロジェクトの規模や目的に合わせて、最適なソフトウェアを選ぶことが重要です。
主要なBIMソフトウェア
BIMデータを利用するためには専用のソフトウェアが必要です。現在、市場には様々なBIMソフトウェアが存在し、それぞれに特徴があります。
Autodesk Revit
https://www.autodesk.com/jp/products/revit/
Autodesk社が提供するRevitは、建築分野で広く利用されているBIMソフトウェアです。建築、構造、設備(MEP)に対応しており、統合的なBIMワークフローを実現できます。特に大規模プロジェクトやチームでの共同作業に適しており、多くの建材メーカーがRevit形式のデータを提供しているため、実務での利便性が高いです。他のAutodesk製品との連携も容易に行えます。
GRAPHISOFT ARCHICAD
https://www.graphisoft.com/jp/solutions/products/archicad
GRAPHISOFT社のARCHICADは、特に意匠設計に強みを持つBIMソフトウェアです。直感的な操作性と豊富な3Dオブジェクトライブラリが特徴で、デザイン性の高い建築物を設計する際に力を発揮します。意匠設計者にとって比較的導入しやすいソフトウェアと言われています。教育版は無償で提供されており、学生の利用も多いです。Mac OSとWindows OSの両方に対応しています。
福井コンピュータアーキテクト GLOOBE
https://archi.fukuicompu.co.jp/products/gloobe/
福井コンピュータアーキテクトが開発したGLOOBEは、日本の建築基準法や設計手法に特化した国産BIMソフトウェアです。日本の実務に沿った機能が搭載されており、確認申請図書の作成など、国内でのBIM活用を円滑に進めるための機能が充実しています。Jw_cadとの親和性も高い点が特徴です。
各ソフトには無料体験版が用意されていることが多いため、目的や操作性に応じて試用し、導入を検討するとよいでしょう。
BIMデータ活用の課題と対策

BIMデータの活用は多くの利点をもたらしますが、導入や運用にはいくつかの課題が存在します。まず、BIMソフトウェアの導入費用や維持管理コスト、高性能なハードウェアの必要性など、初期投資やランニングコストが負担となるケースがあります。また、BIMを扱える専門知識やスキルを持った人材の育成も不可欠ですが、人材不足が課題となっています。異なるBIMソフトウェア間でのデータ互換性の問題や、データ作成の標準化が進んでいないことも、スムーズな情報連携を妨げる要因です。さらに、既存の2次元CAD中心のワークフローからBIMへの移行には、社内体制や業務プロセスの見直しが必要となり、従業員の順応に時間がかかる可能性もあります。これらの課題に対しては、補助金の活用や段階的な導入、人材育成プログラムの実施、IFCなどの標準フォーマットの利用促進といった対策が求められます。
今後のBIMデータの展望
BIMデータは、建築業界のデジタル化を一層推進する鍵となります。今後はIoTやAIとの連携が進み、建物のリアルタイムな情報監視やAIによる設計提案、施工リスク予測などが可能になるでしょう。また、AR/VR技術との組み合わせにより、設計段階での視覚的な確認や現場での情報活用がより直感的になります。業界全体でのBIMデータ標準化や共通プラットフォームの構築も進み、スムーズなデータ連携が実現することで、建設プロジェクトの生産性向上に大きく貢献することが期待されています。BIMデータは建物のライフサイクル全体をカバーするデジタルツインの中核として進化していくと考えられます。


